恋の彷徨者たちの足跡ーー今泉力哉作品における“迷子”と“交差点”についての覚書(『街の上で』論序論)
今泉力哉監督の最新作『街の上で』が公開されたタイミングで書こうと思っていたこと、来春以降に延期となってしまったので一旦この機会にまとめてみました。世紀の大傑作映画につながる、今泉映画論の序論的扱いです。それにしても『街の上で』のTシャツ(大橋裕之のイラスト!)がかわいすぎて、届いてから2週間でもうすでにめっちゃ着てしまっている。
* * *
いきなり結論を言うようだが、今泉力哉監督が撮る映画というのはつまるところ、迷子が迷子のまま世界を彷徨い続ける、「“愛すべき迷子たちに捧げられた映画”である」と言うことができるのではないだろうか。どんなに強い信念を持っていても、今泉映画の登場人物たちは、みな一様に迷子に“させられてしまう”。

『愛がなんだ』のテルコを起点として
最もわかりやすいのが『愛がなんだ』(2019)の山田テルコ(岸井ゆきの)である。彼女は「マモちゃんが好き」という確固たる思いを抱きながらも、その実は酷く方向性を見失ってしまっている女性。例えばマモちゃん(成田凌)に急に呼び出される冒頭の場面では、彼女の意思とは関係なしにこれまた急に外に追い出され、テルコは金麦500m缶を煽りながら夜道を彷徨い、行き場を失ったまま親友の葉子(深川麻衣)に助けを求める。葉子の指示を受けながら下高井戸方面へとタクシーを促すテルコの姿勢は、まさに“迷子”としか言いようがない頼りない顔をしているだろう。
中盤の、機嫌の悪いマモちゃんに朝早く起こされ、土鍋を両手に抱えて道に立ち尽くす場面であるとか、すみれ(江口のりこ)の悪口をひと通りラップで言い終えたあとに「ざまぁみろ」と言葉が反復し立ち止まってしまう場面とかも、テルコ=“迷子”なのだとすればとても象徴的なシークエンスだ。
テルコ:私はどっちかになっちゃうんだよね。「好き」と「どうでもいい」の。だから、好きな人以外は自然とぜんぶどうでもよくなっちゃう
同僚(穂志もえか):自分も?
『愛がなんだ』という映画は、マモちゃんに出会ってしまったテルコが自我すらも含めた全体重をそこに傾けてしまい、だからこそ会社を辞めたり行き場を失ったりしてしまう、徹底した迷子映画なのだとひとまずは結論づけてみたい。そうすると、主に恋愛群像劇を紡ぎ出す今泉映画の共通点が、この“迷子”にあると考えることはできないだろうか。今泉映画の登場人物たちは、恋に迷うだけでなく、一方ではどうしようもなく人生にも迷ってしまう。
『パンバス』で孤独を追求する深川麻衣、『退屈な日々にさようならを』で恋人の過去を辿る松本まりか
すべてを書き出してしまうと長くなってしまうので簡潔に。例えば『知らない、ふたり』(2016)という映画は、昼間の公園のベンチで出会ったある男女の物語が恋愛群像劇のうちの1パートを占めている。そこでは、韓国人青年・レオン(レン)が女性・ソナ(韓英恵)に一目惚れしてしまい、冒頭ではそのストーキング劇→家を見つけるまでが描かれている。その後、ソナの方もレオンの存在が気になりだし、初めて出会った公園を探そうとするのだけれどあの日は二日酔いだったからあんまり覚えてなくて苦戦する、といった物語が展開されていく。要するにレオンもソナも、お互いの存在を知ってしまったことで急に道に迷い始めてしまう。
『パンとバスと2度目のハツコイ』(2017)は、主人公・市井ふみ(深川麻衣)が結婚に疑問を浮かべまっすぐに孤独を追求するものの、同級生の変化に触発されたり妹に心の内を見透かされたりして、徐々に変化すること(≒迷うこと)を強いられていく話(その意味では最近の映画だと『ストーリー・オブ・マイライフ』のジョーの物語にも少し共通する)。
『退屈な日々にさようならを』(2016)では、亡くなってしまった恋人の過去(かつて存在していた生)を求め、原田青葉(松本まりか)が彼の故郷を訪ねるシークエンスがあった。彼女は真っ直ぐにその場所へとやってきたものの、彼が死んだことを彼の家族に知られるとやはり、「あんたおかしいよ。死んでるの知っててそいつの地元にふらふら来てさ、平気な顔して家族に会うって絶対おかしいって。あんたほんとはなにしに来たの?」と問い詰められてしまう。ゆえに目的をなくして迷子にさせられてしまう。でも青葉は何度も問うのだ、「でも生きてたでしょ?」「ほんとうってなんですか?」と。
“迷子にさせられてしまう”という共通点
途中から徐々に文章にも忍ばせましたが、重要なのは彼女たちが“迷子にさせられている”という点なのではないかと思う。
みな真っ当に何かを考えて生きているだけなのだ。それなのに、例えばテルコの場合は「マモちゃんが好きすぎた」ことで仕事ができず、会社を辞めさせられ彷徨者となってしまう。市井ふみは孤独の世界に留まることを許してもらえず、この混沌の世界に放り出されてしまう。原田青葉は彼の過去を見にきただけなのに、彼の家族からは部外者にされてしまう。彼女たちはみな、社会が決めた“普通”から逸脱してしまった、いわゆるマイノリティたちなのだ。今泉映画が温かいのは、そうした彷徨者たちに対しての懐の深い眼差しが存在しているからではないだろうか。
迷子を眼差す迷子……そこに交差点がある
今泉映画が特徴的なのは、ただ迷子を描くだけでなく、その迷子を眼差すもうひとつの視線にカメラを向けているところにある。社会から逸脱してしまった人も、成長できない人も、きっと他の誰かが見ていてくれている。だからすべての人生が肯定され、誰もがその世界の主人公になれる。
登場人物たちの関係性が毎回当然のように三角関係にも四角関係にも発展し、やがて人物関係が一周して外の世界から閉ざされたサークルのようになるのにはおそらくそんな理由があるのだろう。そして今泉映画ではあろうことか、そのみんなを一堂に介させてしまうことで、彷徨者たちの世界を天国に仕立て上げてしまう。
登場人物たちはさまざまな交差点で出会い、やがて散り散りに……。この“交差点”というのはそのままの意味の「道路上」のことだけでなく、カフェや映画館、ライブ会場、居酒屋、ラーメン屋、公園、古着屋、浜辺などなど……今泉映画の登場人物が辿る通過点すべてを内包しゆく。『パンバス』や『愛がなんだ』のラスト付近、その別れのシークエンスでも見られた交差点は、きっと彼女たちの眼差しの交差のために用意されている。
しかしいやはや、登場人物たちが彷徨うだけの映画がなぜこんなにも面白いのか。それにはたぶん、過去の偉大な“迷子映画”たちが答えてくれるに違いない。なぜ映画は迷子を映し出し、登場人物たちは恋に囚われるのか。
丹生谷貴志のヌーヴェル・ヴァーグ論「恋の囚われ」要約
ヌーヴェル・ヴァーグと総称される映画たちの功績とは、「映画を、あるいは映画に付随する生全体を“恋の狂気”にまで推し進めたことである」とする、美学・美術史研究の丹生谷貴志さんのヌーヴェル・ヴァーグ論が激烈に面白かったので要約しておきたい。この文章を読んでいる間ずっと、ゴダール、トリュフォー、ロメール、リヴェットと横並びで今泉映画のことを思い浮かべていた。
まずここで言う“恋の狂気”とはなんなのか。
恋の狂気とはおそらく、ドゥルーズの言うbêtise(獣性)の領域である。つまり、恋が狂気と化すのは、恋が生殖と家族形成という「国是」から切り離される時、快楽主義からさえ見放される時だろう。
これでもまだ難しい。“恋”にはまず、「生殖への準備のために進入してくる」、「家族と再生産と自然共同体の準備としての恋愛」という側面がある。しかし“恋が狂気と化す”とき、それら一切から逸脱した恋は「彷徨いの獣性bêtiseの領域に出て行くのだ」と丹生谷氏は書き連ねる。
彼らのモティベーションは恋の囚われであるということただそれだけであり、寝たいという欲望は決して生殖への欲望には結び付かず、一緒にいたいという渇望は決して家族への欲望に結び付くこともない。つまりは恋の狂気=bêtiseとは、社会から見放され、同時に動物性の穏やかな充足からも見放された状態であり場所であるだろう。(中略)要するに社会にも、その裏面である家族=生殖共同体にも属することのない「無為の、明かし得ぬ共同体」、ただ恋の狂気、恋の囚われであるということだけがそこに残る。純粋化された狂気の恋だけが残る。
家族主義的、社会的規範からは到底切り離された場所にある“恋の狂気”。そして映画とはそもそも、この“恋の狂気”そのものであるからして、それを現前して見せたヌーヴェル・ヴァーグは「映画そのもの」なのであると丹生谷氏は半ば強引に続ける……。
ヌーヴェル・ヴァーグはジャンルとしての恋愛映画とは異質の恋の狂気の世界を開く。そしてそこに彼らの決定的な映画性のしるしがある。と言うのも、キャメラは本質的に恋の狂気の機械だからである。人工性と動物性の中間に開いた宙吊りの眼、見ることへの欲望と盲目が同じものであるような、そうした獣性の瞳としてのキャメラ。純粋化された恋の狂気そのものとしてのキャメラ。だからヌーヴェル・ヴァーグは、映画の本質そのものである恋の狂気そのものを律儀になぞり生きようとし、キャメラの恋の彷徨いそのものを反復し続けるのであり、映画とは恋の狂気そのものに他ならないことを示すのである。
映画は恋の狂気そのものである。それでも今なお、日本でも世界でも*1家族主義に侵された映画が氾濫しているのはなぜなのか。
或る意味では、家族主義的映画の存続は社会学的な問題である以前に、映画のもっともミニマムな属性への恐怖から来ているのかもしれない。世界を恋の狂気とその彷徨いへと変移させてしまう映画的狂気(?)への脅えが家族主義的映画への固執を生み出しているのかもしれない。その意味で、ハリウッドが或いは日本が家族主義的な地平に固執すると同時に真の映画的領域への介入を止めてしまったのは偶然ではないだろう。再び繰り返すが映画は終局的には恋の狂気の場所であり、家族の存続と対立する世界に他ならないだろうから。……
そしてだから、その意味で、陳腐な言い方だが、ヌーヴェル・ヴァーグは映画を映画そのもの、映画以上でも以下でもないもの、つまりは恋の狂気として露出させたという点でなお「未来の映画」に属するのだと言うことも出来るに違いない。すべての映画が恋の狂気となる時、始めてヌーヴェル・ヴァーグは完了することになるだろう*2。(後略)

*1:ここで丹生谷氏は小津安二郎の異様さや、『クレイマー、クレイマー』『普通の人々』などのピューリタン的家族映画にも言及している。
*2:『ユリイカ 総特集ヌーヴェル・ヴァーグ30年』丹生谷貴志「恋の囚われ」p156-163
2020年5月のカルチャー雑記②リモート映像作品の救い

世間で流行りの『愛の不時着』『梨泰院クラス』(第1話だけ観た)には手を伸ばさず、『ハーフ・オブ・イット』も観たけど微妙にハマらなかったり、『鬼滅の刃』も『約ネバ』も『ヒロアカ』もアニメには興味をそそられなかったり、コロナ以前にかろうじて製作された良質な作品にことごとく嫌われてしまった自分は、結局なにを観てたかというと旧作映画とYouTubeばかり観ていた。あとメルカリの沼に落ちてしまって、昔のユリイカとかリュミエールとかswitchとかを買って映画批評をむさぼり読んでた。
そのなかでも「リモートで製作された映像作品」というのがあって、“今の時期はこれを観ておくべきだろう”という確固とした意思があったわけでもないのだけど、気づいたらそればっかり観ていたことになる。かまいたちとかニューヨークとか、芸人がzoomを使ってする生配信動画を合わせれば、5月に摂取したカルチャーはほとんどがYouTubeで完結していたかもしれない。期せずしてYouTube関連の記事をたくさん書いたりしていて、もう僕はYouTube系ライターになりつつあるし(本当は映画ライターになりたい)。
でも6月に入ってドラマも映画もちょっとずつ動き出してきているので、いったんの区切りとして良かった作品をリストアップしてみた。何人かのTweetでも見たように「映像作品にいかに撮影が必要か」というのを思い知らされもしたけど、今できることに最大限に取り組んだこの作品たちはカルチャーの火種を絶やさない唯一の救いだったし、それぞれに強く光り輝いていたと思う。
⑥ロロ連作短編通話劇『窓辺』第1話「近くに2つのたのしい窓」
— kohei hara (@shimauma_aoi) 2020年5月28日
⑦今だから、新作ドラマ作ってみました 第1夜『心はホノルル、彼にはピーナツバター』
⑧上田慎一郎『カメラを止めるな!リモート大作戦!』
⑨ジャルジャル『ハズレの先生にリモート授業される奴』
⑩近藤啓介『動物暴走教師』(SHINPA)
二宮健監督が主導している「SHINPA」という映画上映プロジェクトがある。昨年のゴールデンウィークには二宮監督の過去作が一挙上映されていて、何日か通ったのも記憶に新しい。コロナ禍でいち早く、大きな映画プロジェクトを立ち上げたのがこのSHINPAだった。「在宅映画制作」と題して、延べ24人の映画人が新作映画を「オール在宅制作」で撮り下ろし。二宮健を筆頭に、深田晃司、今泉力哉、松居大吾、柄本佑、渡辺大知といった豪華な面々が5月1日から代わる代わる新作をYouTube上で発表した。24作品もあるので半分も観れてないけど、飛び抜けて面白かった作品がいくつかある。そのひとつが岩切一空監督の『第七銀河交流』。モキュメンタリーとホラーとアイドル映画が混じり合った大傑作映画だった。
岩切監督というのは、そもそもがこの、モキュメンタリーとホラーとアイドル映画を混淆した作品をつくる作家である。『花に嵐』では、早稲田の映画サークルに入った“僕”(岩切一空本人役)がある1人の女の子にカメラを向けることでこの世界の最深部に誘われていく様が描かれている。次作の『聖なるもの』もまぁ乱暴に言ってしまえばほぼ一緒。はてなのエントリーにも書いたのだけど、彼の作品は映画史を純粋に辿りながら、時おり今どきのYouTube的な要素が覗く点が刺激的。彼がTwitterで「だいにぐるーぷ」や「レインボー」といったYouTubeチャンネルの名を挙げて「映画みたい」と時々呟いていることにもわかるように、彼にとっては映画とYouTubeには恐らくさして境界線はない。そうした、「映画にYouTube」を取り入れてきた岩切監督がついに、逆に「YouTubeに映画を持ち込んでしまった」のが本作『第七銀河交流』なのである。このコロナ禍でしか実現しなかった企画かもしれないけど、岩切作品とYouTubeがついに真の意味で出会ってしまった。その作品には、“第七”芸術たる映画が、3つのパラレルワールドーーいわば映画の光の“3”原色ーーを通して再び私たちが出会う未来の銀河を描く、壮大な世界が紡ぎ出されていた。
今泉力哉『MILK IN THE AIR』、深田晃司『move / 2020』、近藤啓介『動物暴走教師』等もよかったけど、岩切監督のやってることが異次元すぎて他が霞んでしまう。素晴らしいものを観た。あと坂元裕二のリモートドラマ『Living』もめちゃよくって感激した。特に1、2話ね。ズバズバぶっ刺してくる言葉の威力が半端ない。あとあと、Webで公開されてる映画だと、ANAの『再見』という映画がけっこうよかったです。監督・竹内里紗(『21世紀の女の子』「Mirror」)×脚本・宮崎大祐(『TOURISM』)で、ジャック・リヴェット『北の橋』みたいな彷徨いの映画を撮り上げてしまっていた。
www.ana.co.jp
YouTubeで観れる岡田惠和脚本、吉田羊×大泉洋の『2020年 5月の恋』と、「超、リモートねもしゅー」の2作目をまだ観れてない。そうこうしてるうちに映画館に行ける日々が戻ってきたね。3か月ぶりの映画館はアップリンク吉祥寺で『パターソン』を観て、これは日常を取り戻すにはぴったりな映画だな、と思った。初めて観たときは眠たかったけど、今回は妙にしっくりきた。
外を覗くこと、扉を開くこと、書くこと……『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』雑感

『ストーリー・オブ・マイライフ』はさまざまな“関係性”を描いた映画である。僕は若草物語の原作を知らなかったから、最初はその登場人物の多さと人物関係がわからなくてちょっと焦った。でもヒロインである次女・ジョー(シアーシャ・ローナン)を中心として、長女と次女の、次女と三女の、次女と四女の、娘たちと母の、そしてジョーやエイミー(フローレンス・ピュー)とローリー(ティモシー・シャラメ)の関係性が軽妙な手さばきで描かれていくから、みるみるうちに物語に引き込まれてしまう。7年前と現在ではその関係性も、人のいる場所も大きく変わっている。しかし時おりジョーが走ったり、電車に乗ったり、アイススケートをしたり、馬車に乗ったりすることで、離れ離れの人と人が結びつけられていく。
本作の特徴的な演出として、「窓から外を覗く」「窓を開ける」「敷居をまたぐ」といった、“境界線”とその“越境”を表出したシーンの頻出が挙げられるだろう。


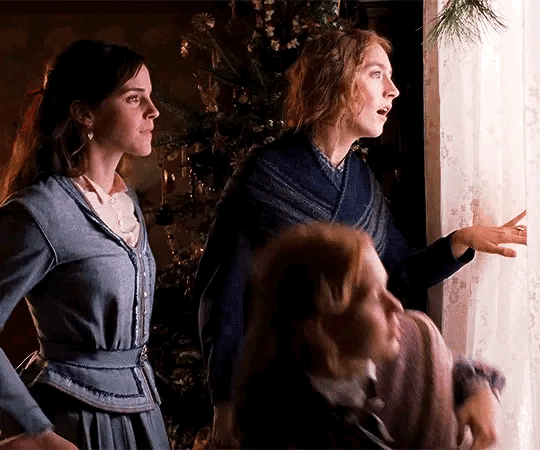
人と人の間には決してわかりあえない、混じり合うことを許さない壁が存在しているのは確かだろう。それが本作で言うところの「窓」だとして、しかし彼女たちはいとも簡単にその境界線を越えてみせてしまう。
たとえば冒頭、作品を持ち込む際に扉の前でひと息つく場面(→そして彼女は作家の扉を開く)にはじまり、物乞いを受けて四姉妹が朝食を持っていき、その姿をさらに上流階級のローリーが窓から覗く場面(要するに身分や階級の壁を越境している)や、ジョーとローリーが出会い(舞踏場から一歩足を踏み入れた部屋のなかで彼女たちは出会う)、中の人に気づかれないようにバルコニーでダンスする姿、あとはジョーやお父さんが帰ってくる場面の開扉もそうだし、ベスが回復し、一方では亡くなってしまう一連のシーンもわざわざベスをいったんベッドから退け、ジョーが階下のダイニングを「覗き伺う」行為にドラマを宿している。そうした境界線を越える/越えない描写の積み重ねによって、彼女たちの多様な関係性が徐々に炙り出されていくのである。

長女は服飾、次女は文学、三女は音楽、四女は絵画と芸術一家の四姉妹が非常に愛らしいのだけど、なかでもジョーの「書く行為」に授けられたメッセージはやはり見逃すことができない。ちなみに、長女が生地を買ったり売ったり、三女がピアノを弾いたり弾けなかったり、四女が「三流の画家になるくらいならキッパリとやめてやる」と言い切ったりと、本作においては「人物と芸術」の関係性の描き方も丁寧で、特に長女の「生地を買ったり売ったり」だとかは一見無駄な動きに見えて、案外重要なストーリーを紡ぎ出していると思う。
そのなかでもジョーの「書く行為」に絞ると、彼女の作品は友人に否定されてしまったり、編集者にも大幅に削られてしまったり、あるいは妹に焼かれてしまったり散々な目にあっている。それでも彼女は書くことを諦めず、最後には『Little Women』を出版するに至る。彼女の「書く行為」のなかでも最も重要だと感じたのが、ローリーに想いを伝え直す終盤の手紙の場面。結局あれは、坂元ドラマ的な「届かなかった手紙」として漂流し、自らによって破り割かれてしまうわけだ。そしてその「書いても自分の本当の想いは相手に届かない」というのは、彼女がこれまで文学をやってきたなかでの記憶とまったく合致する。
それでも、というか、そうだからこそ、彼女は最後に物語を紡ぎ出すのだろう。そのことは、決して取り戻せない過去の時間や離れ離れになってしまった関係性を越境する行為にも繋がるだろうし、一方向に規定されない自由な女性の生き方をいつまでだって追究し続けるジョーの姿勢を言い表しているだろう。もう元には戻らない時間と、その愛おしい過去を自らの言葉で語り直し、その言葉を強く抱きしめて明日を生きていくある女性の話。書く行為に託された美しさやたくましさにもちろん僕としては心を鷲掴みにされてしまった。
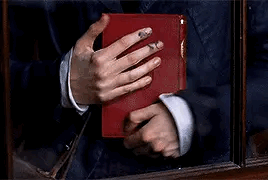
2020年5月のカルチャー雑記①リアリティショーとお笑い
信じられないスピードで情報と流行が入れ替わる現代にあって、今回のコロナは強制的に時流にストップがかかるいい機会だと最初の頃は楽観視していた。でもそんなことはあり得なくて、排水溝をなくした浴槽のなかに水が流れ込み、そして溢れ出ていくのをただただ黙って見ているしかないのが現実だった。自分の心のなかも同じで、毎日毎日何かについて思考を巡らせているのだけど、なんか吐き出し方がわからないというか、吐き出すことにまったく意味を感じないというか、かなり混乱していた。そうこうしているうちに世界はまたとんでもない早さで動き出して、そのスタートダッシュをし損ねてしまった気がする。世界にも自分にも、多くの悲しみがあり、怒りがあり、死があった。現在進行形で。もちろんネガティブなことばかりなんかでは決してなかったんだけど、負の力はすぐに正(生)の力を覆ってしまう。苦しかったのは、そんなときいつもなら助けてくれる愛するカルチャーが、正常な形をしていなかったことだ。というよりも、カルチャーを含むいろんなものに対して、その歪な原型に盲目だったのかもしれない。だからこそ今月も、カルチャー日記を書きそびれてしまいそうになりながらやっぱりカルチャーに向き合わないといけない。まとまった文章を書く気力と勇気が今はないので、3つのエントリーに分けて思考の断片を撒き散らします。①リアリティショーとお笑い、②リモート映像作品の救い、③恋の囚われとヴェンダースと。
*
『テラスハウス』に出演していた木村花さんが亡くなってしまった。このことに対してもしかしていちばん許せなかったのは、「彼女がSNSで誹謗中傷を受けていた事実」を僕が全然知らなかったことかもしれない。(これはテラスハウスメンバー全員なのだけど)TwitterもInstagramもフォローしてなかったから、事の残酷さに気づくまでにいくつかのネット記事で経緯を辿る時間が必要だった。いち視聴者としてはここで、「コンテンツにはのめり込んでいたけどそれと出演者の人生は別個のものだと思っているから、出演者が亡くなったことは寝耳に水だった」と開き直ってスルーすることができるかもしれない。でもそれはただ無知をひけらかすだけで、きっといちばん卑怯なことだと思う。実際、花さんがSNSに苦しんでいる描写はおそらく作品中にはほとんどなかったものの、彼女以外の他のメンバーがそれで深く傷ついている描写はこれまでにも嫌と言うほどたくさんあった。そして僕はそういう番組構造であることを承知したうえで、外(SNS)の世界だけを捨象してただ作品にのめり込んでいた。僕はテラスハウスが大好きだったし、出ている人たちも大好きだった。そして好きすぎてリアルサウンドで月に一回レビューを書いていた。にも関わらず、テラスハウスと他のコンテンツの最も差別化できる部分であり、いちばん劣悪な点でもあった「SNSが番組に強い影響を及ぼしていた悲惨な事実」を、僕はただの一度も書くことができなかった。山ちゃんの声が大きくなりすぎて危険だ、みたいなことしか書いてなかった。マジで馬鹿。
書くことを決めずに書き出しているから話が変な方向にいってる気がする。とりあえず自分はどうしようもない馬鹿だって話で、それについてまずは反省し尽くす時間が必要なのだけど、それと同時にテラスハウス以外にも危険なカルチャーがあることを認めなければいけない。SNSが劣悪なものだというのは周知のなかで、そのSNSが強く影響を及ぼしてしまうカルチャー。アイドル、YouTube、お笑い…。SNSで知り合ったファンにグループの内部情報を話してしまったあのアイドルのことをどうしても思い出してしまうし、ずっと見過ごされてきただけだったことが明らかになったあのラジオ番組の失言も、10年前に聴いてた時にはなにも疑問を浮かべなかったのだろうと思う。テラスハウスの山ちゃんの発言も、やっぱり聞いてて「ん?」と思うことは多々あったから、それがたとえお笑いに昇華されていようと少なからずよくない影響を及ぼしていたことには違いない。カルチャーと個人はSNSがある以前から互いに影響を及ぼし合ってきた。それもグラデーション的な心の変化を与えるものとして。良くも悪くもカルチャーがないと生きていけない自分は、その存在の危うさに常に向き合っていかなければいけない。いま最も危ないな、と思いながらも強く引き込まれているのがお笑い。なにも考えずに笑えるのがいちばん楽しいに違いない。でもいつだって、ふとした瞬間に覚える違和感には敏感であらなければならない。もう2度と大好きな人とカルチャーを失わないために、変わり続ける世界のなかで取り残されてしまったカルチャーのあり様を監視し続けなくてはいけない。
あとSNSはみんなやめたほうがいい。140字で政治を語ったり批判したりすることはできても、政治を批判してる人に反論したり、その人にまた反論したり、そんな建設的な会話ができると思うなよ。僕にはもう、Twitterの政治論争は戦争にしか見えない。頼むから自分の近くにいる人と徹底的に議論を交わしてくれ。嫌なら毎回1万字くらいの反論でやりあってほしい。そんなこと言ったってそんな未来はきっと訪れないのだけど。
ポップカルチャーをむさぼり食らう(2020年4月)

映画館に通えなくなってから早1か月半くらい。それまでは週末に2〜4本の新作映画を観ていた生活が一変し、演劇もライブも軒並みなくなって、世界中の人々と同じように僕も一日中家にこもっている。ふと気づくと1か月以上、対面で知り合いと会ってない。仕事も完全テレワーク。そのあたりは言うほど寂しくないからどうでもいいのだけど、問題は僕の好きなカルチャーが一体いつ戻ってきてくれるのか、という漠然とした不安のほう。僕と同じように週末に映画や演劇、ライブに行きまくっていた人がたくさんいたはずで、そのぶんの経済の動き、文化の流動がなくなったいま、どのようにカルチャーは再生していくのか。まったく予想ができないでいる。
小規模な映画配給会社や大手シネコンのほうもかなり心配ではあるけれど、ひとまずはミニシアター支援のクラウドファンディングにその月の映画代ぶんくらいだけ支援した。大阪のミニシアターに1時間と2000円を費やして通っていたあの時間がなければ、きっと僕はこうしてカルチャーにどっぷり浸かることはなかっただろう。クイックジャパンウェブでミニシアター支援のいくつかの方法をまとめた記事を書いています。ぜひ。
それにしても「ミニシアター・エイド基金」のクラファンのリターン(「サンクス・シアター」という名称がしあわせ)が申し訳ないくらいに豪華。深田晃司、瀬田なつき、三宅唱、濱口竜介などなど日本映画界を今後20年背負っていく監督たちの初期作品はめっちゃ観たいし、みんなにも観てほしい。昨年のマイベストワン映画である『ひかりの歌』(杉田協士監督)(未DVD化)も入っているので、観てみてほしいです。坂元裕二ドラマに匹敵する“まなざし”の映画で、先を生きていくお守りになるはず。
新作映画や演劇、ライブを観れないことに悲嘆しつつも、実はその一方で少し安心している自分もいる。それは、しっかりと腰を据えて一本の映画に向き合ったり、長すぎる映画史のなかにある未見の映画を観たり、それに対応する映画批評を読んだりする時間がこれまではまったく取れなかったから。何も知らないことに気づく2年の社会人生活を経て再び大学生のような生活に引き戻された僕は、怠惰なりにも旧作映画を掘ったり、批評雑誌「ユリイカ」の文章を読み込んだり(メルカリで過去のやつもたくさん買えることに気づいた)、文章を書いたりしている。
長くがむしゃらに社会人として走り続けてきたみなさんにおかれましても、ちょっとした心の休暇の日々になることを願っています。ほんとうは外に出て、めいいっぱいヴァカンスできれば言うことないんだけどね。でも「なにかをしなければいけない」(僕にとっては毎週末映画を観ることも「新作映画を観にいかなければいけない」という義務感になっている部分が少なからずあった)というストレスから解放される時間は、老後を迎える前の人生のうちに何度かはあってもいいと思う。
* * *
今月もたくさんカルチャーに接することができたんだけど、それを振り返る前に、合間合間の暇を持て余し尽くした時間に観ていたものを先に書きたい。それというのも、エビ中と、ぼる塾にどっぷりなのだ。
先月のカルチャー日記にもそのハマるまでの経緯を書いた私立恵比寿中学は、その後もYouTubeで公開されているライブ映像やメンバーのインスタなんかをみてハマり散らかしています。ハロプロと違って、やっぱりストリーミングで音源を聴けるのもいいですよね…。なんせ僕がアイドルを好きになる第一条件は楽曲や歌唱力の部分なので。正統に(?)『エビクラシー』の「感情電車」や「紅の詩」あたりを聴き込みつつ、最新アルバムの『playlist』がすばらしくよくてめっちゃ聴いてる。多彩なアーティストとのタッグ曲がたくさん収録されているアルバムなのだけど、iriプロデュースの「I’ll be here」とポルカプロデュースの「SHAKE! SHAKE!」、PABLOプロデュースの「PANDORA」あたりの曲調の違いが楽しすぎる。違いというか、完全に各アーティストの曲調に憑依しつつ、滲み出る6人の個性ある歌声が耳を幸福にしてくれる。“幸福なコラボレーション”としか言いようがない。なかでもやっぱり小林歌穂さんの歌声が大好きです。
YouTubeの「ぼる塾チャンネル」にハマった。昨年のM-1予選の動画でしんぼるのネタを観ておもしろいなぁと思ってたんだけど、まさか4人組になっているとは思わなかった。UPされている動画は全部観てしまって、アメトーークやしゃべくりでの活躍も追っていました。とにかく、「あんりが有能すぎる」ということを言っておきたい。まぁ見てのとおりなんですけどね。アメトーークではそいつどいつ竹馬やザブングル加藤、三四郎小宮など、しゃべくりでは世間知らズ西田あたりと非常にポップな“敵対”関係を見せてズバズバいけるあんりのツッコミ力をアピールする一方で、そのしゃべくりでの「海外ロケに行くなら体を張るより普通に旅行したい」という発言にゆるさを見せたり、視聴者はキャラクターを捉えやすいうえにそのキャラクターは現代性を帯びていていい意味で複雑。
そういう柔軟性は漫才において田辺さんとはるちゃんという全く性格の異なる変人を扱うなかでも現れているのだけど、そのなかでも感心するのは“ちょっと危険性を孕んでいる”はるちゃんの扱い方。ぼる塾がポテトチップスを平らげる動画のなかで『きのう何食べた?』の話題になって、ジェンダー的な観点から話が食い違いそうになるのだけど、あんりは一瞬戸惑いつつそれを軽やかに軌道修正する。きっとはるちゃんは思ったことを口にしてしまう人だから、あんりの自己批評性や柔軟性が助けになるのだろう。「ニューヨークのニューラジオ」で語っていた結成秘話も面白かった。「あんりが言うとなんでも面白くなる!」と嬉しそうに話すはるちゃんがかわいい。
【ゲスト:やさしいズ&ぼる塾】ニューヨークのニューラジオ特別編#17 2020年3月18日(水)
演劇
家にいるのに、演劇をめっちゃ観れたひと月だった。YouTubeで公開されている『生まれてないからまだ死ねない』で初めて範疇遊泳の演劇を、CSで録画(昨年の今ごろだけど…)していた『ヒッキー・カンクーントルネード』『て』でこちらも初めてハイバイの演劇を、1日だけ映像配信されていた『スーパープレミアムソフトWバニラリッチ』でこれまた初めてチェルフィッチュを観ることができた。
ハイバイの家族劇はどこか歪な形をしていて(『て』の二重構造など)、初見としてはちょっと見づらかったけどまさしくそれが魅力でもあるだろうから他も観てみたい。チェルフィッチュは次回公演があれば必ず観にいきたいってほどよかった。これもハイバイと同じく、というよりそれ以上に構成がカオス(コンビニという普遍的な場所を舞台としながらも、登場人物たちは必ず身体の動きを伴った奇妙な会話を繰り返す。バッハの音楽に載せて)で最初は戸惑ったけど、その煩雑さ(簡単な言葉で言うと多様性)こそが美なのだと訴えてくるようで、バチッと僕の思考にはまった。それにしてもカオスだった。

劇団が映像配信で新作を発表する動きも多くありましたね。そのなかでもいちばん早かったんじゃないか?という特急の仕上げを見せたのが根本宗子さん。「超リモートねもしゅー」と題して、完全リモート制作の作品を作り上げた。『あの子と旅行行きたくない。』という作品。会社の同僚であるという4人が、社員旅行を計画しながらも行き先の議題でバチバチに意見が食い違い、ちょっと険悪になったりしながら旅行へ行くそのときまで会話を繰り広げる。2015年(?)あたりに作られた作品をリモート作品風に書き直したものらしく、このお話も2015年(コロナ以前)からはじまる。それが終盤で華麗に時間を経過させ、コロナ禍を経由しながらまだ見ぬ未来へと至るまでを描いていて、コロナ禍が過ぎたら旅行に行こうね〜という安易な感傷に浸らせない点がよかったと思う。ねもしゅーの演劇は『墓場、女子高生』しか観たことがなかったから、こういう機会に作品の雰囲気に触れられたのはうれしい。しかも登場人物4人全員が『墓場、女子高生』にも出てた役者だとあとで知った。キャラクターが最高でしたね。
ロロの通話劇、連作短編としてシリーズ化していくという『窓辺』の1作目「ちかくに2つのたのしい窓」もよかった。今月号のクイックジャパンを読んで三浦さんの思考の軌跡の一端(その大きな変遷)を読み取ることができたのだけど、なるほど本作もいつものロロのようでやはり全く新しく、今までにない感情を与えてくれる。リモート通話という2つの窓。その“あわい”にある空間を演者ふたりと共有することで心が一体化していく時間。ロロの演劇はいつもうまく言葉で言い表せなくってもどかしいけど、これからもそういう新しさを見せつづけてほしい。
映画
ちゃんとした“新作映画”としては、『ワンダーウォール 劇場版』のみ(オンライン先行上映会みたいなやつで)観ることができた。京都大学吉田寮の「寮生追い出し」問題を題材にし、4月10日に上映を予定していた(?)作品。2018年にNHKで放送されたドラマを、再編集と追加映像により劇場版とした映画だ。12月末くらいにアップリンクでドラマ版がスクリーンにかかっていて観に行ったから物語に関しての新鮮さは全くなかったものの、分断が加速する世界にあって、この映画は多くの人に観られるべきだと改めて思った。だからこういう上映が困難ない状況になってしまったことが残念でならない。
比較的新しい作品で言うと『ザ・ライダー』も面白かった。昨年末くらいからアマプラでレンタルのみの配信をされていた作品が、Netflixに追加されていました。映画評論家の村山章さんが昨年のベストか何かに選んでいて気になっていたやつ。主人公であるロデオ乗りの青年が、競技中に大きな怪我を負ってしまい、そこからどう這い上がるか、危険なロデオをやめるか続けるかという判断を迫られながら、ときに自分の信念と人生との折り合いをつけて生きていく様が、雄大で美しい自然を背景にして描かれていく。“カウボーイらしさ”(≒“男らしさ”)とは何かを問う物語であり、現代に生きるものとしての苦悩と、ほんとうにかっこいい生き様とは何かを探る美しい映画でした。監督は中国系の女性・クロエ・ジャオさんで、この映画が評価されてマーベル新作『エターナルズ』の監督に大抜擢されたそう。主人公や主要登場人物をその物語の着想となった本人(=素人)が演じているというのがすごい。昨年TIFFで度肝を抜かれた『わたしの叔父さん』と同じ作り方をしている。

最近はヌーベルヴァーグまわりの映画を掘ることに必死。大学生のときにゴダールの映画を観てさっぱり理解できなかった(今もゴダールには手が伸びないけど)ところから、フランスのヴァカンス映画に魅了される期間を経てようやくヌーベルヴァーグに回帰することができた。リヴェット、ロメール、ブレッソン。ちょっと時代と国は外れるけどキェシロフスキの映画にもハマった。キェシロフスキの映画を4本観たなかでとびきり面白かったのが『愛に関する短いフィルム』。ある女性の部屋を覗き見する青年が主人公(最近の邦画で言うと『アンダー・ユア・ベッド』が近い)で、その女性と青年の“成瀬『乱れる』的”な交錯ドラマが描かれていく。87分という映画の短さにしてとても濃厚で情動的な映画だった。終盤がとにかくすごい。

ロベール・ブレッソンの映画も3本観て、脱獄劇の『抵抗』がいちばんよかったかな。空間の描写すべてに緊張感がある。ジャック・リヴェットは『彼女たちの舞台』と『北の橋』を観て、まだまだ全然なんの映画なのか意味がわからないでいるのだけど、登場人物が魅力的で会話と動きが自由で観れてしまっている。ユリイカ等の評論を読んでいると遊戯的な、ゲーム的な世界が構築されているのだそう。「ヌーベル・ヴァーグ30年」という特集のユリイカを読みながら勉強している。ヌーベルヴァーグの代表格であるトリュフォーも実はほとんど観れていないから少しずつ手に取っていきたい。
久しぶりに増村保造の映画も2本観た。初期の『青空娘』と中期の『「女の小箱」より 夫が見た』という若尾文子とのタッグ作を続けて。両方大傑作なんだよな〜。若尾文子の顔と身動きが両作で全然違うのも素晴らしいし、それによって増村の作風の変遷、時代ごとの多面性にも気づかされる。「わたしと仕事、どっちが大事なの?」の最大究極形にして、最もしとやかにそれを問い詰める『夫が見た』の若尾文子にはマジでしびれた。溝口の『赤線地帯』、川島雄三の『女は二度生まれる』『しとやかな獣』あたりで見せる何にも動じない強さも素晴らしいけれど、やはり増村作品に生きる若尾文子はひと味もふた味も違う。「命を賭けて自己主張をする個人としてのヒロインーー観念だけでなく、肉体を持った女性ーー」*1との評論は的を得ている。ちゃんと弱さも垣間見せる点が他と違うと思う。
川島雄三の『洲崎パラダイス 赤信号』も最高に面白かった。人生の迷い人である男と女が、立ち止まったり離れたり、再会したりをただ繰り返す映画。その無様な反復が人生を言い得ている。橋の映画。

あとは、好きな映画を見返す日々。ロメールの『海辺のポーリーヌ』とか、ギヨーム・ブラックの『女っ気なし』とか(DVD買っちゃった)、いちばん好きな青春映画の『あの頃ペニー・レインと』とか、濱口竜介の『PASSION』とか。それとは別に『テラスハウス』の軽井沢編(大好き)も見返していて、ヴァカンス的なもの、空虚なものを欲しているんだろうなぁと自認する日々です…。『街の上で』の公開(時期未定)に向けて今泉監督の映画も見返している。
bsk00kw20-kohei.hatenablog.com
演劇のいくつかの動きと同じく映画界でもリモート制作の作品がいくつか公開された(リモートカメ止めまだ観てなかった!)。なかでも好きだったのは、二宮健監督がYouTubeにUPしたクレイアニメ『HOUSE GUYS』。映画上映企画のSHINPAが催している在宅映画制作の取り組みで、その主導者として口火を切った二宮監督。『ピングー』みたいな懐かしのクレイアニメを、ひとりで制作するにはかなり時間を要したであろうクオリティの高さで作り上げていて、その話の内容もかなりよくて子どもに見せたくなった。子どもいないけど。同イベントの今泉監督『MILK IN THE AIR』も手放しで絶賛したい。ひたすらかわいい。
ドラマ
相変わらず『有村架純の撮休』が面白い。第4話のみ微妙というか酷いとすら思ったけど、横浜聡子監督の第5話「ふた」、今泉監督の第6話「好きだから不安」、津野愛監督の第7話『母になる(仮)』はどれも個性に溢れていて素晴らしかった。フェイクドキュメンタリーの特性を活かした「嘘」と「本当」にまつわる話の第7話が特に好きかも。突如家にやってきた少女との「偽物の母娘」関係を通して、有村架純が原初的な「演じること」=「嘘」の本質、その幸福にたどり着くまでを描く。オレンジジュースの挿話がみずみずしくて、12月の夜から急に夏へとジャンプするラストが秀逸なのだ。

今クールは、役者がそのまま本人役を演じるフェイクドキュメンタリー作品が多い。そしてどれも一定の水準をクリアしている良作。安達祐実が主人公の『捨ててよ、安達さん。』には大九明子監督が入っていて、軽やかなコメディとファンタジーの折り合わせが絶妙にハマっている。何よりも毎回オープニングがいい。Huluでは『住住』のシーズン2も始まった。正直言ってシーズン1のほうが百倍ワクワクしたし、同じような展開の使い回し感もすごいのだけど、新しく登場する日村さんと水川さんのキャラクターはとてもいい。全員既婚者(しかも新婚)という特性をどうにか生かしてくれないもんかなぁと思う。前シーズンは「同じマンションに住んでいる」という絶妙にありそうなファンタジーが楽しかったんだよなぁ。
リアルサウンド で『美食探偵 明智五郎』のレビューを毎週書いてるのだけど(撮影開始が早かったらしく放送休止を免れている)、これがけっこう面白いです。最近の日テレ日曜10時枠はずっと観てこなかったしちょっと観て嫌いだなって思う作品が多かったから、好きなドラマでよかった。何よりヒロインの小芝風花さんがさいっこうにかわいいのよ。アニメみたいなツインテールの様式美に弾ける笑顔。演技もうまい。虜です。
お笑い
かが屋、ニューヨーク、ぼる塾、などなど最近よくお笑いにハマっている影響から、彼らが出ているテレビ番組も久しぶりに観るようになった。ニューヨークは出る番組すべてでちゃんと仕事をしていて頼もしい。『爆笑問題のシンパイ賞‼︎』とかめっちゃよかったな…。第7世代に数えられていない、いわゆる6.5世代みたいな枠の代表格として存在感をあらわにしていて、怒りと皮肉の芸風もうまく効いていて周到に立ち回ってる。ニューヨークはYouTubeのラジオが面白くて、そこでオズワルド伊藤(伊藤沙莉の兄)の有能さを知るなどした。アメトーーク鳥貴族芸人でもそのツッコミ力でバリバリ活躍していて嬉しかった。テレビでいうとドリームマッチと相席食堂(野球回)、テレビ千鳥(コメンテーター選手権)が面白かった。
かが屋のコントの魅力をあぶりだそうとして『みんなのかが屋』にUPされている動画をすべて見てレビューするという(想定より恐ろしく時間かかった)無謀なことにも挑戦しました。『文化祭』がいちばん好きかも。加賀顔面グラデーションの傑作。
bsk00kw20-kohei.hatenablog.com
YouTube
面白かったYouTubeのほんの一部。芸能人YouTube論を聴けるニューヨーク×カジサックコラボ。女王蜂を初めて聴いて未知すぎて耳取れそうになったファーストテイク。独特なナレーションが癖になる料理系YouTuberの1人前食堂(リーズーチーの日本版、いわゆる実録版リトルフォレストをやろうとしている)。映画評論家の大寺先生の映画授業を聴けるありがたい番組、ゆるく考える映画史。おしゃれすぎる編集とスターウォーズ的映画/絵画紹介がツボな和田あやちょの動画(あやちょが紹介していた『赤い風船』も最近観て、絵本のような色彩美、お話の美しさに見惚れた)。などなど。
さーて、映画館はいつ行けるかな〜〜。
東京で“迷子”になる人々/今泉力哉『退屈な日々にさようならを』

「でも、生きてたでしょ?」と何度も問う松本まりかが印象的だ。今はもういないけど、たしかにあのとき生きていて、生きることと死ぬことが肯定でも否定でもなくすべて等価に見つめられている感覚。生と死、双子、福島と東京のふたつの顔、同性愛やバイセクシャル、自分と他者、震災前と震災後ーーあらゆるものは反発しながらも混淆していく。今泉作品は、空間を重視した「人物の物理的移動」の多さだけでなく「時間の不可逆性/その堆積」を感じさせる点からある種の“ロードムービー”のような側面も垣間見せるが、本作でもそれは顕著だ。東京で(主に恋愛に)“迷子”になる人々の姿は『パンバス』『愛がなんだ』『街の上で』に通じ、かつてあった生を求めて福島へ向かう松本まりかの姿は『サッドティー』『アイネクライネナハトムジーク』『his』などの作品につながっていく。迷子と答え、それは言うなれば生と死。今泉力哉は、映画を通してまぎれもなく人生を描いている。
見知らぬ地に私たちは新しいものを見ることができない。既に見てしまったものの残像を認めるだけだ。空間を移動しながら私たちは時間の旅をしている。それもただ遡るだけの。……ロードムービーとはエイリアンの物語であり、ノスタルジアの物語である。人はその行く先々で人々と違う時間を生き、またその地に自分の過去を、既に見た風景を追認しようとする。新しいものは何もない。そこでは空間が過ぎていくのではなく、過去の時間がループになった映像のように何度も繰り返される。……
ーー「還る旅ーー異端的旅映画」『月刊イメージフォーラム』1992年5月号より抜粋
引用したのは、高円寺の古本屋「古書サンカクヤマ」で見つけた映画雑誌の一文。渋谷にある(シアター)イメージフォーラムが90年代に発刊していた月刊誌ですね。「映画で地球の歩き方」という特集でヴィム・ヴェンダースを中心に“旅映画”の多様な側面が論じられていて、これに触発されて今泉監督の映画も広義の“ロードムービー”なのではないか?という仮説を立てるに至ったわけです。
上林栄樹さんによって書かれた上記の文章では、ロードムービー(≒人生)とは時間の旅であり、それはただひたすらに「過去を追認するためだけの旅」であると結論づけられている。たしかに、と思うところも、ほんとうに人生はそれだけなのか?と首を傾げてしまう部分もある。
今泉力哉監督の映画では、非常に多い頻度で、この「過去」という概念の残酷さ、それゆえの尊さをあぶり出そうとしている。試しに乃木坂46 12thシングルに収録された「かなしくない I’m not sad」というPV中のセリフを引いてみよう。
好きな人が いま目の前にいて
好きな人も 僕を好きだと言う
だけどいまは すでにもう過去だから
いまの気持ちはわからないし そしてそれももう過去だ
セリフというか正確には、北野日奈子が好きな人に向かって歌うちょっとした歌(今泉力哉作詞作曲)なんだけど。こうした、いまは好きだけどすぐ先の未来ではどうなってるかわからないという、今泉映画の登場人物を貫く時間不可逆的な姿勢は、過去を過去のものとして現在から切り離し、積極的に未来を生きようとする意思を感じさせる。その一方で、『退屈な日々にさようならを』で「でも、生きてたでしょ?」と問い続ける松本まりかのように、「そこに確かにあったもの」を見捨てようとはせず、これも積極的に抱きしめて生きようとする。これは決して矛盾するものではない。上記引用文の反駁をさせていただくと、「過去を追認しながらも、“まだ見ぬ”未来を生きていくことは可能」であると今泉作品は示しているし、そのようにして過去と現在、未来を等価に並べる姿に強く僕は共感させられているのだと思う。
ずっとそこにある「過去」の尊さを認めながら、更新され続ける「未来」を生きようとする。それは時として過去を追認するものではなくなるから、“迷子”の旅となり、行き場を見失うこともあるかもしれない。今泉作品が描くのは、その迷いの旅路である。迷いながらも、それでも歩き続けていく。その先の未来が更新され続けることを、ただひたすらに信じながら。
<関連エントリー/記事>
bsk00kw20-kohei.hatenablog.com
bsk00kw20-kohei.hatenablog.com
bsk00kw20-kohei.hatenablog.com
bsk00kw20-kohei.hatenablog.com
かが屋のコント26本レビュー
2週間ほど前から『みんなのかが屋YouTube channel』でかが屋のコントが大量放出されている。これがほんとうにどれも面白くて味わい深くて愛おしくて。感激しっぱなしだったので現在UPされている26作品を全作レビューしてみた。特に好きなのは、『市役所』『親友』『イヤホン』『俳優』『バイトのシフト』『面白い男の人が好き』『文化祭』『田舎の事件』あたりです。ぜんぶ好き。
(※2021年8月追記。いつの間にか『みんなのかが屋YouTube channel』のネタ動画が全て消えってしまったのですが、そのほとんどは『マセキ芸能社公式チャンネル』にも上がっているのでそちらをご覧になりつつ短評をお楽しみいただければと思います)
『リズム』
『学校へ行こう!』でおなじみのリズムゲーム「みのりかリズム4」に興じる5人の若者。なぜかタナ(加賀)にだけ出番が回ってこず、オカ(賀屋)をはじめとする4人で盛り上がりを見せ、タナは次第に苦い表情を見せはじめる。タナも観客も最初は「ハブられてる?」という疑念を抱くわけだけど、ときにそれを覆す「本音」がかが屋のコントの持ち味。それをオカに言わせないのもいいし、彼らがこれまで積み上げてきた時間の堆積が鮮明にうつる。
『市役所』
市役所で窓口対応をする女性(賀屋)と、彼女にあることを伝えにきた彼氏らしい男性(加賀)。「だから舞台が市役所だったのか」という中盤の驚きと、その加賀の企てをひっくり返す賀屋のひと言が楽しい。お互いに一度ずつ言葉を噛んでしまったりするもののサムい感じにならないというか、それすらも愛らしいほど日常がコントに溶け込んでいる。匿名性を帯びた市役所のなかで、ただ2人だけに注がれたスポットライトが眩しい。
『親友』
これは序盤からエンジン全開でおもしろいやつ。サイレントでもいい。お互いに「親友を元気づけたい」「親友に元気なところを見てほしい」と思っている思考の美しいズレが及ぼす行動のズレ。最後に思わぬところでプチサプライズを起こすのも、このコントの醍醐味である「視覚」効果によるもの。
『大富豪』
タイトルのとおり大富豪で遊んでいる数人の男たち。彼女と電話する加賀によりゲームが中断されたことで、仲間から非難の声が浴びせられる。中立の立場にいる賀屋はいつだってその誠実さが似合っているし、加賀の子どものような泣き芸はそれだけでおもしろい。かが屋のコントのギミックである「反転」がそのまま大富豪の「革命」に繋がっているのが単純に巧い。
『唇』
唇を「ぶ〜」ってする子どもと、「それやるとたらこ唇になっちゃうよ」と注意するお父さん(賀屋)。舞台は電車で、その親子の横の席にはたらこ唇の加賀が座っているという、設定勝ちのコント。終始、悲しいのか嬉しいのか、怒っているのかが曖昧な表情を見せる加賀の複雑さがいい。あと押される芝居がうますぎる。
『合唱』
合唱コンクールに向けた練習をする生徒たちと先生(賀屋)。そのなかでただひとり「できてる」と指名されたときの優等生(加賀)の優越感とちょっとの恥ずかしさ。「歌うこと」に対する想いをいちばん持っているのであろう先生の行動も熱すぎてちょっと恥ずかしいけど、瑞々しくも感じる。
『電車にて』
電車にて、イチャイチャするカップル(男性:賀屋)とそれを横目で見る加賀。相手に夢中で距離感がバカになった賀屋が加賀に接触してしまったり、賀屋が、現実にいる“ちょっとヤバいやつ”を快演している。彼に宿る二面性とさらにそれを裏切る終盤の展開も、賀屋のいい人とも悪い人とも捉えづらい複雑な顔面がうまく体現してみせている。
『自転車』
自転車を置いてコンビニかなにかに買い物へ行く加賀。帰ってくるとその自転車の前で男女が恋愛のイザコザを起こしているという、これまた現実にちょっとありそうなシチュエーション。“ことの傍観者”=加賀を徐々に“当事者”に仕立て上げていく手法は『唇』と同じで、かが屋のコントの姿勢が垣間見える。ちゃんとどん兵衛を食べちゃう演出も余韻があっていい。
『イヤホン』
もうすぐ引越ししてしまう加賀を呼び出す賀屋。AirPodsを自慢するため?かと思いきや、そこから二転三転するげに秀逸なコント。賀屋の愛らしい行動をさして何度も「キモい」と表現する加賀の、本当は複雑な心情をその言葉に閉じ込める姿。それは、かが屋のコントを見ている間に私たち観客が抱く「感動」でも「驚き」でもある複雑な感情を「笑い」として表出しようとする姿勢ととても似ている。泣ける展開でもとりあえず笑いたくなる。
『俳優』
エキストラの加賀と演出家の賀屋。急遽大事な役を演じるはずの役者が飛んでしまって、その代わりを「すべてのセリフを覚えている」という理由から加賀が引き受けることになるが…。これはさらっと展開される序盤の1分くらいの会話がのちのち効いてくるので、YouTubeで繰り返し観られるのはうれしい。エキストラという代替可能な存在を通して描くことで、かが屋のコントが見せる「人間の悲哀」が境地に達していると思う。
『バイトのシフト』
コンビニかなにかのバイト仲間である男(加賀)と女(賀屋)。バイトのシフト変更でサプライズ的に訪れる2人の時間。かが屋のコントはその登場人物2人がどういう関係性なのか、想像を促す冒頭の余白ある時間が楽しい。予想を覆されても、予想と同じでもどっちでもうれしいし。ここでも、一度傍観者にされてしまった男が当事者に引き戻される瞬間がハッとする。憎らしいほどうまい。
『面白い男の人が好き』
かが屋『面白い男の人が好き』コント 2019.09 資料映像
加賀くんの表情の変化をずっと見ていたい、初対面の男女が徐々に心を通じ合わせていくさまを捉えた最高のコント。少し不器用な男性(加賀)が発するボケが、女性(賀屋)に掬い上げられることで会話のラリー、心のグルーヴが生じる。お笑いの美しさの原点を見ているようでもある。
『文化祭』
かが屋『文化祭』コント 2018.01 かが屋『文化祭』コント 2018.01 資料映像映像
文化祭でのクラスの出しものを決める投票にて。“脱出ゲーム”と“たこ焼き”でデットヒートを繰り広げるなか、加賀の表情が暗くなっていく…。青春すぎる!!!!!!! これもずーっと加賀くんの表情が変わっていくグラデーションを見ていたくなる。すべてを知っている賀屋のイケメンっぷりがすごいし、「高くね!?」なラストも愛らしい。
『缶コーヒー』
演劇仲間のふたりの男。ベンチに座って落ち込んでいる後ろ姿を見せる賀屋に、缶コーヒーを持っていこうとする加賀の描写からはじまる。これも前の2本と一緒に「加賀顔面グラデーション3部作」と名付けたい。“賀屋には見えていない”ということを利用した身体の動きもすばらしい。
『田舎の事件』
大傑作長編映画を観たあとかのような余韻。単純なプロットの巧さでいうと、ほかのコントとは一線を画しているかもしれない。「町のくら寿司が閉店する」という小さいけど大きな事件を契機に、お父さん(加賀)とお母さん(賀屋)、くら寿司の店長や彼らの子どもとの交流が描かれる。人を思いやることがどれだけ美しいことか、再確認させられるコントだ。かが屋のコント美学である「反転」がバシバシ決まりながら、訪れる感動のラスト。小津の映画だよこれは。
『彼女の部屋』
彼女の部屋で過ごすあるカップル。男(加賀)が部屋を後にすると、女(賀屋)があることをしはじめる…。これも何度も観ているけど、本音を言うときの賀屋くんの必死さと、信じようとしない加賀くんの幻想垣間見える姿がツボ。真実を知ってちょっとだけ幻滅しているような加賀/それに気づかず連発する賀屋の構図が愛おしい。
『花束』
キングオブコントで披露されたネタだけど、初披露の際の映像らしく構成やラストが少し違う。しかし、かが屋を観ている観客のリテラシーの高さには毎度驚くな。花束を抱えて俯く男性とそこに「蛍の光」が被さるだけですべてを理解してしまえるのはすごい。1回目でそれだけウケると、それは2回目の明転では大爆笑ですよね。演者と観客の信頼関係が生んだ傑作。逆でもおかしくない配役、どう決めているのか気になってくる。
『ギャグとかやろうか?』
かが屋『ギャグとかやろうか?』コント 2020.02 資料映像
これは10年付き合った彼女にプロポーズしてフラれてしまった加賀くんの実話がベースになっているのでしょうか。本編は7歳のころから19年付き合って、それで昨日フラれて落ち込む加賀と、励ますためにギャグを連発する賀屋の関係性が映し出される。ギャグのクオリティがどんどん増していくのがこのコントの最大の面白さ。
『爆弾』
ものものしいタイトルとは裏腹なほっこりする親子コント。息子が母親に好き勝手怒鳴り散らかしている場面は胸がきゅーっと縮こまり、その熱意と同等のものを母親がぶつけた瞬間に想いが広く開放される。パイの実で気を紛らわせようとするキュートなお母さんはいつもエプロンが似合う。
『終電』
終電を逃すか逃さないかという時間帯に居酒屋で、付き合うか付き合わないかの微妙なラインの男女が一つひとつ確かめるように言葉を重ねる。鼻血が出るというある種のわかりやすさを提示することで、その奥に複雑な想いをうまく隠しているように見える。ほんとうにかが屋は、どこにでもいそうな“普通の人”を体現するのが巧い。
『下ネタ』
「下ネタは言うなら夜にして」と言う賀屋と、昼下がりのカラオケで下ネタを連発する加賀。「夜は新聞配達してるから…」というマイノリティの意見が表に出ていく気持ちよさもさることながら、「わかってくれるだけでいいから」という、あらゆる多様性に目を向けたコミュニケーションの話になっていく展開が興味深い。すべてを理解するのは不可能だから、ただわかってさえもらえればいい。
『大事な話って?』
大事な話があると賀屋に呼び出された加賀。しかし賀屋の電話が鳴り止まず、なかなか話を切り出せない。これはファーストボケが強いタイプのコント。そこまでの長いフリがすばらしく、加賀くんはずっとかわいそう。ただそのかわいそうに対する対価が思い切っていてちょっとゲスいのと、それを軽く受け入れられてしまうパラドックスが奇妙で面白い。
『かわいい』
居酒屋で飲む先輩(賀屋)と後輩(加賀)。彼女がいるのに他の女の子をみて「かわいい」と漏らす加賀に、信じられないほど熱いテンションで怒りだす賀屋の人間味が愛おしいコント。熱い人なんだなと思っていたら次第に、「付き合うこと」への美しい幻想を持つ人だと明らかになっていく過程。この人のために誠実でいようと思わせてしまう賀屋のキャラクターがかわいい。
『洗濯機』
『かわいい』に続いて、イノセントな賀屋先輩のフィーチャー作品。新品のドラム式洗濯機を肴に酒を飲もうとする先輩と、戸惑いながらも迎合していく加賀。わかりあえなさを貫く洗濯機の作動音が切ない。
『合コンの話』
前2本に続く「イノセント賀屋3部作」でした。合コンの話をしていた数人の男のところに友だちの賀屋がやってくるものの、なぜか「無人島にひとつだけ物を持っていくとしたら?」の話題にすり替えようとする加賀以外の仲間たち。周到に避けていた「本音」が明らかになったときが哀しいけれど、賀屋の何も知らなさに救われもする。
『兄弟』
パントマイムを覚えた小学生くらいの弟(加賀)が高校生くらいのお兄ちゃん(賀屋)を呼び出してその腕前を披露しようとするコント。いつもならばお兄ちゃんじゃなくて母親が出てきてもおかしくないのだけど、ここではその兄弟独自の関係性を見せようとしている。親よりもお兄ちゃんとかに褒められるほうが確かにちょっとうれしいよな、という実感がこもっていて好き。『親友』とかもそうだけど、かが屋はこの“関係性”に迫るコントがとてもいいのです。
僭越ながら、クイックジャパンウェブではじまったこちらの記事の取材・テキストを担当しています。めっちゃ面白いし加賀さんらしい感じになっています。