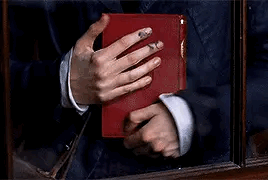『ストーリー・オブ・マイライフ』はさまざまな“関係性”を描いた映画である。僕は若草物語の原作を知らなかったから、最初はその登場人物の多さと人物関係がわからなくてちょっと焦った。でもヒロインである次女・ジョー(シアーシャ・ローナン)を中心として、長女と次女の、次女と三女の、次女と四女の、娘たちと母の、そしてジョーやエイミー(フローレンス・ピュー)とローリー(ティモシー・シャラメ)の関係性が軽妙な手さばきで描かれていくから、みるみるうちに物語に引き込まれてしまう。7年前と現在ではその関係性も、人のいる場所も大きく変わっている。しかし時おりジョーが走ったり、電車に乗ったり、アイススケートをしたり、馬車に乗ったりすることで、離れ離れの人と人が結びつけられていく。
本作の特徴的な演出として、「窓から外を覗く」「窓を開ける」「敷居をまたぐ」といった、“境界線”とその“越境”を表出したシーンの頻出が挙げられるだろう。


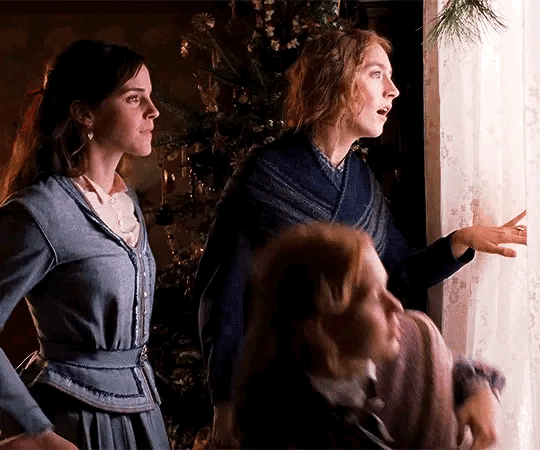
人と人の間には決してわかりあえない、混じり合うことを許さない壁が存在しているのは確かだろう。それが本作で言うところの「窓」だとして、しかし彼女たちはいとも簡単にその境界線を越えてみせてしまう。
たとえば冒頭、作品を持ち込む際に扉の前でひと息つく場面(→そして彼女は作家の扉を開く)にはじまり、物乞いを受けて四姉妹が朝食を持っていき、その姿をさらに上流階級のローリーが窓から覗く場面(要するに身分や階級の壁を越境している)や、ジョーとローリーが出会い(舞踏場から一歩足を踏み入れた部屋のなかで彼女たちは出会う)、中の人に気づかれないようにバルコニーでダンスする姿、あとはジョーやお父さんが帰ってくる場面の開扉もそうだし、ベスが回復し、一方では亡くなってしまう一連のシーンもわざわざベスをいったんベッドから退け、ジョーが階下のダイニングを「覗き伺う」行為にドラマを宿している。そうした境界線を越える/越えない描写の積み重ねによって、彼女たちの多様な関係性が徐々に炙り出されていくのである。

長女は服飾、次女は文学、三女は音楽、四女は絵画と芸術一家の四姉妹が非常に愛らしいのだけど、なかでもジョーの「書く行為」に授けられたメッセージはやはり見逃すことができない。ちなみに、長女が生地を買ったり売ったり、三女がピアノを弾いたり弾けなかったり、四女が「三流の画家になるくらいならキッパリとやめてやる」と言い切ったりと、本作においては「人物と芸術」の関係性の描き方も丁寧で、特に長女の「生地を買ったり売ったり」だとかは一見無駄な動きに見えて、案外重要なストーリーを紡ぎ出していると思う。
そのなかでもジョーの「書く行為」に絞ると、彼女の作品は友人に否定されてしまったり、編集者にも大幅に削られてしまったり、あるいは妹に焼かれてしまったり散々な目にあっている。それでも彼女は書くことを諦めず、最後には『Little Women』を出版するに至る。彼女の「書く行為」のなかでも最も重要だと感じたのが、ローリーに想いを伝え直す終盤の手紙の場面。結局あれは、坂元ドラマ的な「届かなかった手紙」として漂流し、自らによって破り割かれてしまうわけだ。そしてその「書いても自分の本当の想いは相手に届かない」というのは、彼女がこれまで文学をやってきたなかでの記憶とまったく合致する。
それでも、というか、そうだからこそ、彼女は最後に物語を紡ぎ出すのだろう。そのことは、決して取り戻せない過去の時間や離れ離れになってしまった関係性を越境する行為にも繋がるだろうし、一方向に規定されない自由な女性の生き方をいつまでだって追究し続けるジョーの姿勢を言い表しているだろう。もう元には戻らない時間と、その愛おしい過去を自らの言葉で語り直し、その言葉を強く抱きしめて明日を生きていくある女性の話。書く行為に託された美しさやたくましさにもちろん僕としては心を鷲掴みにされてしまった。