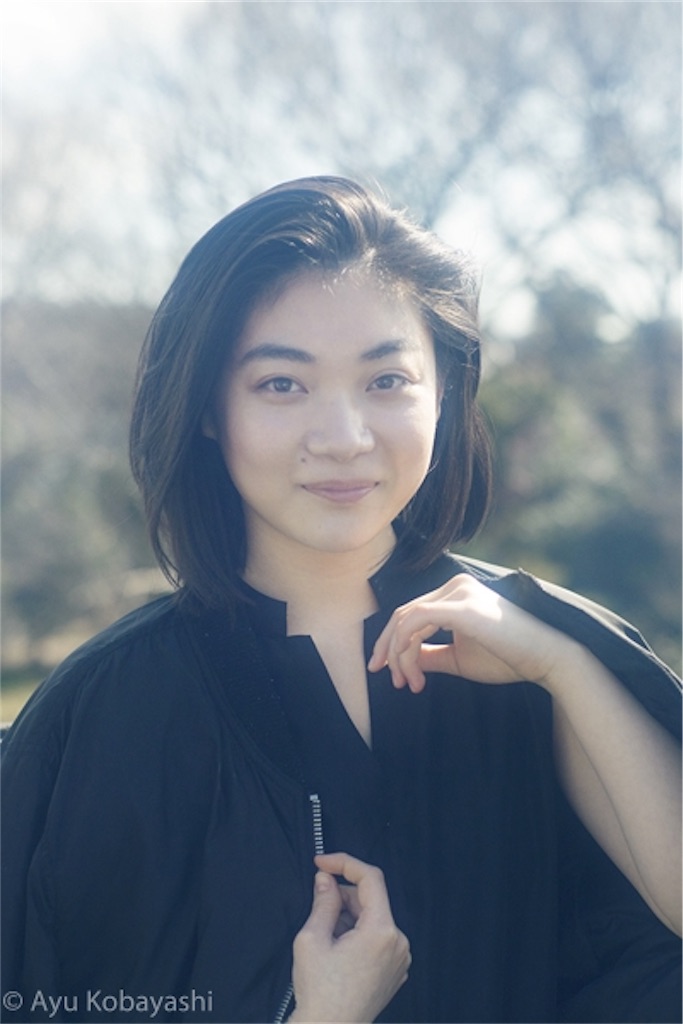2018.6.12

先日報道ステーションに是枝監督がゲスト出演していて、その時に語っていた言葉はどれもが印象的だった。その中でもキャスターからの「どうして家族を撮るんですか」という問いに対する答え。
「家族ってやっぱりおもしろいんですよ。ひとりの男性を見てみてもその人が父親であり、夫でもあり、また息子、叔父、いとこといろんな役を演じている。人の多面性を撮るにはちょうど良くて、それが浮き彫りになるのはおもしろい」
みたいな。なぜ自分が家族映画を好んで見るのか、その答えがこれだったんだと妙に腑に落ちたものです。ある人物の多様な側面が浮き彫りになるのが家族という共同体で、その「家族」を突き詰めていくとその先に大きな社会が見えてくる。
* * *
その是枝監督も愛したエドワード・ヤンの遺作『ヤンヤン 夏の思い出』。鑑賞後の今、人生のすべてを垣間見たような不思議な感覚を抱いている。
本作に登場するのは、あるひとつの家族と彼らを取り巻くさまざまな人々。本作はこの多様な人物たちの群像劇として進行していき、是枝監督の言葉のように人間の多面性を描き出していく。特にN.J.(題名にもあるヤンヤンという少年の父親)にスポットライトを当てる時間が多く、また彼のキャラクターは特に多面的に撮られ、印象的だ。
本作における彼の役柄を挙げてみると「ヤンヤンにとっての父親」「ヤンヤンの祖母にとっての息子」「ヤンヤンの母親にとっての夫」「ヤンヤンの叔父にとっての義兄」「高校時代の恋人にとっての元恋人」と書き出すと止まらないくらい。そしてこの映画を観ていると気づくのは、人生において役柄が多ければ多いほど=多面的であればあるほど、その生き様は豊かで、幸せに違いないということだ。まだ若造なので本当のところはどうなのか分からないけど、他人と多く、密に接している人ほどその人生は幸せ(不幸も内包した“豊かさ”がある)なんだろうなと、感じずにはいられなかった。
ヤンヤンの母親が家を出て行ってしまう理由なんかもここにあるのではないだろうか。母親の前では彼女の娘でしかいられないことへのもどかしさ。そこからの解放を求めるという行動。これは『恐怖分子』において「家を出て行ってしまう」彼女と彼にも同じことが言える。少ない役柄しか演じれないように強制されてしまうと、途端に精神が崩壊してしまうのだ。
本作では出会いと別れ、恋と失恋、生と死などさまざまな事象が画面を往来していく。ときに淡く、ときに厳しく、優しく、辛く。感情もさまざまに往来していく。楽しくて優しいだけではなく、残酷すぎる現実ももちろん訪れる。そうであっても、この静かに躍動する画に、僕の心は掻き乱されてしまった。いつの日か、エレベーターから出てきた人が2、30年前の元恋人だった、みたいな経験をしたいなと、そんな気持ち悪いことを考えさせられてしまう、不思議な映画だった。






![お引越し (HDリマスター版) [DVD] お引越し (HDリマスター版) [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51rFdomWfyL._SL160_.jpg)
![ヤンヤン 夏の想い出 [DVD] ヤンヤン 夏の想い出 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51dR0rI%2B4tL._SL160_.jpg)